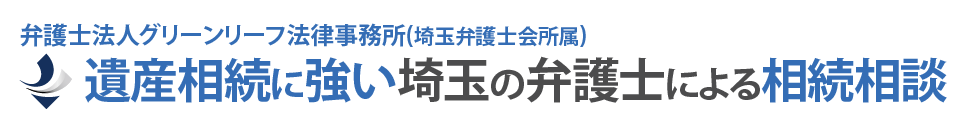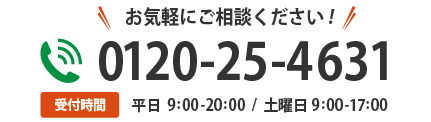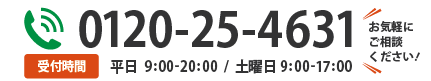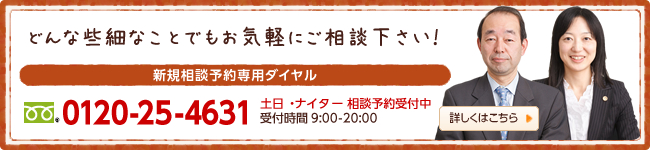紛争の内容
ある日突然、司法書士からご相談者様のもとに、「あなたの伯母さんが亡くなりました。相続手続きを進めるので相続するかどうか返信下さい。」という手紙が届きました。
この伯母さん(以下、被相続人とします。)と相談者様はほとんど面識がなく、特に高齢によって施設に入ってから10年以上、まったく交流がありませんでした。
被相続人には、施設に入って以後、成年後見人が付いていたということです。連絡をしてきた司法書士は、被相続人の成年後見人であり、被相続人の財産を現在も管理しているため、相続人にこれを引き継ぐべく、本件の相続人らに連絡をしていたようです。
ご相談者様がひとまずこの司法書士に連絡してみたところ、「相続人のうちの一人が、(一人で)遺産を全てもらうと言っている。詳細やその理由は分からない。遺産の分け方について相続人同士で話し合いが付かないのであれば、私としては相続人のどなたにも遺産をお渡しすることができない。また、相続人のどなたの味方もすることができないし、話し合いの仲介もできない。」といった趣旨の説明があったそうです。
この相続人の方(以下、Aさんとします。)についても、ご相談者様はほとんど面識がありませんでした。
また、Aさんがどうしてそういったことをご主張されるのかも想像がつきません。
分からないことだらけになり困ったご相談者様は、弊所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談者様は、被相続人やAさんと面識がなく、そのご事情もよく分からなかったため、遺産分割交渉をご依頼されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士において、書類の取り寄せや成年後見人だった司法書士への聴き取りをして、相続人の範囲と相続財産の確認を行いました。なお、相続人は、ご依頼者様とAさんの2人だけでした。
また、Aさんに連絡をとり、遺産分割に関するご主張とご希望を伺いました。
Aさんのご主張を整理すると、
①被相続人に対して病院代などの立替金債権がある
②被相続人の葬式代を負担したので遺産から補填してもらいたい
③被相続人の今後行う四十九日や一周忌などの法要の費用を確保したい
といったもので、合計で約550万円程度でした。
一方、遺産は預貯金のみで、全部で500万円弱程度でした。
そのため、Aさんは「遺産を全てもらいたい」というご希望になったということでした。
上記のAさんの主張は、一見すると正当なようにも見えます。
しかしながら、法的には、上記①~③のいずれも遺産から回収できる費目ではありません。
①については、被相続人側から見ると、立替金を返還しなくてはならないという「債務」ということになります。分けることのできる金銭債務(可分債務といいます。)は、相続開始時(被相続人死亡時)に、各相続人にその相続分に応じて当然に相続されます。したがって、Aさんは、Aさんとご依頼者様にそれぞれ立替金の半分ずつを請求できるということになります。遺産から回収するわけではありません。
②については、お葬式は被相続人が亡くなった後に行われるものであり、被相続人がお葬式のための契約を結ぶわけではありません。お葬式代は、原則、喪主・施主といったお葬式を主宰する人が契約者として負担するものとされています。したがって、Aさんが被相続人のお葬式を主宰した以上、お葬式代はAさんの負担となり、遺産から回収できるものではありません。
③については、被相続人のお墓などを承継して法事を行っていく「祭祀承継者」が負担するものになります。祭祀承継者が祭祀を承継したとしても、その分、遺産を多くもらえるという制度にはなっていません。したがって、遺産から回収することはできないということになります。
Aさんには、上記のような、法的な帰結についてご説明いたしました。
また、ご依頼者様には、Aさんには上記のようなご事情があったということをご報告し、本件の解決策について相談させて頂きました。
本事例の結末
本件では、上記のとおり、Aさんの主張は法的には認められないことになります。
そのため、遺産の配分は、ご依頼者様とAさんとで半分ずつ(250万円弱ずつ)ということになるのが原則です。
ただ、ご依頼者様としても、上記①の立替金の半分については自分に配分されるはずの遺産から支払いたいこと、及びすでに負担が生じてしまっているお葬式代についてはある程度遺産から補填した方が好ましいこととのお考えがありました。
このことから、原則通りの分け方ではなく、上記①の立替金の精算も含めて、Aさんが400万円弱、ご依頼者様が100万円弱、取得する内容で遺産分割協議を成立させました。
本事例に学ぶこと
Aさんのおっしゃった上記①~③のようなご事情は、多くの相続の場面で見受けられるものです。
法的な帰結としては、いずれも遺産から回収するものではないとされますが、本件のように、相続人同士で話し合い・譲り合いができるのであれば、柔軟な解決をはかることも可能です。
相続の場面で何か疑問が生じた場合には、ぜひ弁護士まで一度ご相談ください。まずは「法律による原則はこうなります」というのを明らかにすることが、相続問題の解決のはじめの一歩になると思われます。
弁護士 木村 綾菜