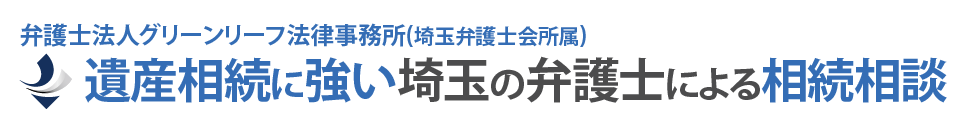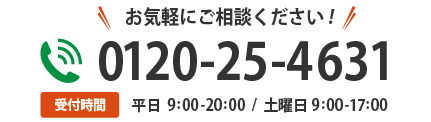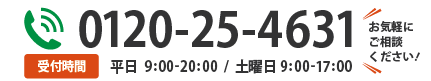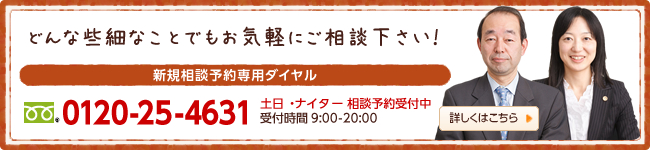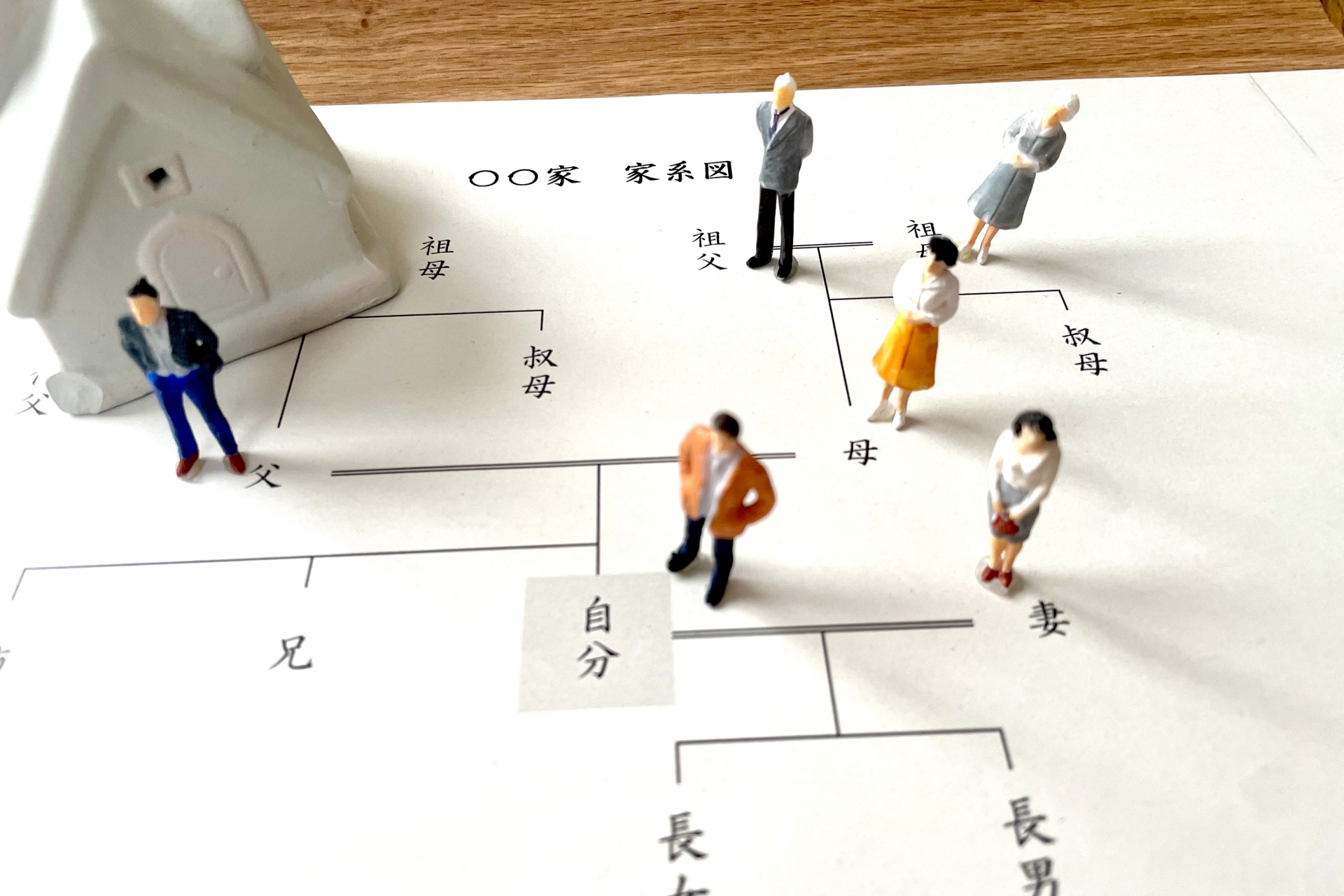
相続欠格とは、相続制度における重大なルール違反を行った相続人から相続権をはく奪する制度です。この記事では、どういった行為をした場合に相続欠格に当たるのか(欠格事由)、相続欠格に当たった場合の詳しい効果などを解説します。
法定相続人であれば相続権は安泰?
例えば親が亡くなった場合、遺言などが無ければ、その子どもが第一順位の法定相続人として、相続をすることになります。
この場合の「子」は、法律上の血縁関係がある「子」であれば良く、例えば「親と同居しているか否か」「家(墓)を継いだか否か」などは問題になりません。
子が2人いて、一方の子と親は親密であるが、もう一方の子と親は仲違いしており疎遠であるといった事情があったとしても、どちらも「子」であることには変わりはなく、相続が発生すれば、(配偶者がいない場合には)2分の1ずつの割合で相続することになります。
このように、民法で定められた「相続」という制度が、個別の事情をある意味で無視して相続権を与えていることから、「どんな事情があっても相続人になってしまうのではないか」と考える方もいるのではないでしょうか。
確かに、民法はある程度までの事情は(ある意味で)無視して相続権を与えています。
しかし、やはり“程度を超えた者”に対しては、相続権を与えるのは不適当であると定められています。
それが「相続欠格」という制度です。
相続欠格とは?

相続欠格とは、相続という制度の秩序を乱した相続人の相続権をはく奪する、民法上の制裁制度です。
民法891条本文
次に掲げる者は、相続人となることができない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
上記の条文どおり、相続欠格に当たった相続人は、当然に相続権を失います。
ここで「当然に」と言ったのは、特に何らの手続も不要であるという意味です。
例えば「相続欠格を認定してもらう審判を家庭裁判所に申し立てる」とか、「遺言で『この相続人は相続欠格である』と書く」とか、そういった特別な手続きは必要無いということです。
ただし現実には、相続欠格だと言われてしまった相続人は、相続欠格には当たらず自分は相続権を有すると反論して紛争になることが多いと思いますので、その者の相続権・相続分が不存在であることを確認する訴訟をする必要が出てくる可能性はあります(ややこしいですが、これはあくまで、「相続権が無い(=相続欠格である)」という事実を『確認する』訴訟なので、訴訟をしなければ相続欠格の効果が発生しないということではありません。)。
どんな行為をした人が相続欠格に当たるのか?

相続欠格の事由、すなわち「こんなことする人には相続させません!」という行為は、民法上、下記の5つと定められています。
民法891条各号
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
以下、少し詳しく見てみましょう。
1号について
①は分かりやすいですね。被相続人を死亡させることで遺産を得ようとする者に相続させるわけにはいきません(条文に「故意に」とあるため、殺人についてのみならず、遺産を得る・相続上得をするといったことも意図することが必要と言われています。)。
また、「相続について先順位若しくは同順位にある者」とありますが、これはその者がいた場合には自分が相続人になれない者(例えば第3順位である兄から見た、第1順位である子(甥姪)や第2順位である父母)や、自分と同順位で遺産を山分けすることになる者(例えば第1順位である子が複数人いる場合)が該当します。そういった人物を無理矢理押しのけて遺産を得ようとする者についても、やはり相続させるわけにはいかないですよね。
1号は小説やドラマといった創作物ではよく見られる類型ですが、内容がかなりハードですので、現実にはさすがに稀なケースとなっています。
2号について

②は被相続人が殺されてしまったときにその犯人を故意に告発・告訴しない相続人には相続させない、というような内容になっています。
まず状況が異例中の異例ですので、実際には2号はほとんど適用がないのではないかと考えられます。
また、犯罪を捜査する義務があるのは私人ではなく捜査機関(検察や警察)です。その義務を実質的に私人に負わせようとするこの条文には問題があると考える説もあるところです。
3号について
③は、被相続人が自由な意思で遺言をすることを妨げてはならないというものです。
例えば、被相続人が妻Aに多くの遺産を遺したいと考えて遺言を作成しようとするときに、子Bが自身の得られる遺産が少なくなってしまうことを嫌って、被相続人を脅して遺言書を書かせなかったというようなケースでは、この3号の欠格事由にあたるものと考えられます。
遺言も相続制度の大事な一部ですから、自由な遺言を妨げる者は相続制度そのものを脅かす者であるとして、やはり相続させるわけにはいきません。
4号について
④は③と似ています。こちらは、詐欺や脅迫によって被相続人の自由な意思を曲げさせて、遺言をさせたり、遺言を撤回させたりした場合に該当します。
3号は「させなかった場合」、4号は「させた場合」ですね。
これも3号と同様、相続制度への脅威となりますから、相続させるわけにはいきません。
5号について
⑤も、③④と同様、遺言に関するものです。
3号・4号は被相続人にアプローチして、遺言をさせなかったり、させたりした場合でした。
一方5号は、遺言書に直接アプローチをする場合です。
すなわち、遺言書を一から偽造した場合や、被相続人の作った遺言書に手を加えた場合、被相続人の作った遺言書を捨てたり隠したりした場合が、この5号に該当します。
ただし、この5号も、1~4号までと同様、相続制度を蔑ろにする人物かどうかという判断基準を含んでいます。
そのため、単に遺言書を偽造したり破棄隠匿しただけでなく、そのことにより相続に関して不当な利益を目的としていることが必要とされています。
したがって、例えば、子A・B・Cが相続人である相続の場面で、実は「すべての遺産はAに相続させる」という内容の遺言書があるにも関わらず、きょうだい間の仲が悪くなってしまうことを恐れたAが、法定相続分どおりに遺産を分けようと考えて、この遺言書の存在を隠していたという場合には、遺言書を隠すことでAには相続上の得は生じないため、Aは相続欠格とはならないと考えられます。
相続欠格に該当した場合どうなるの?

相続欠格者本人への影響
上記のような欠格事由に当たった場合には、冒頭でも述べた通り、その相続人は当然に相続権を失い、相続人ではなくなります。
相続人ではなくなるということは、預貯金や不動産といったプラスの財産を相続できないのはもちろんですが、借金といったマイナスの財産も相続しないことになります。
ただし、相続欠格であることは、戸籍にもどこにも記載されたり公表されたりしませんので、第三者からは一見では分からないようになっています。
そのため、本当は相続欠格に当たり相続人では無くなっているにも関わらず、そのことが知られないまま遺産分割協議に参加して遺産を引き継いだ場合には、「相続人ではない人が遺産を持って行った」という状態として対応されることになります。
相続欠格者の子による代襲相続は可能か
例えば、父親が亡くなり、その子が法定相続人となる相続の場合、子の中にすでに亡くなっている者があるときには、さらにその子(被相続人から見れば孫)が代襲相続人として相続人になることになります。
では、このケースで、法定相続人である子が相続欠格に当たり相続人では無くなった場合、その子(被相続人から見れば孫)は代襲相続ができるでしょうか。
「相続制度を蔑ろにした者の子どもには相続させたくない」と考える方もいるかもしれませんが、民法は「親は親、子は子」とそれぞれが独立・個別の存在であることを前提にしています。
すなわち、相続欠格は欠格者当人だけに当てはまるものであり、その子には引き継がれません。悪いのは、実際悪いことをした親だけ、ということですね。
そのため、民法の代襲相続の規定(887条2項)は相続欠格を代襲原因としており、上記のケースでは、被相続人の子が相続欠格に当たり相続人でなくなった場合には、その子(被相続人から見れば孫)が代襲相続人として相続をすることになります。
ちなみに、「相続放棄」の場合は、代襲原因になっておらず代襲相続ができません。
これは、相続放棄をする場合には、多くの場合で債務超過(借金が多い)などの問題があるため、相続放棄の場合も代襲相続がされる制度設計にしてしまうと、多くの人が相続放棄をしなくてはならなくなるため相当ではないとされたからだと言われています。
まとめ

いかがだったでしょうか。
相続欠格は、相続制度における重大なルール違反を行った相続人から相続権をはく奪する制度です。
相続は経済的利益が絡むこともあり、親族間で骨肉の争いに発展することもありますから、こういったある種の制裁を用意して規律(ルール)を守らせるということも必要だったのだと思われます。
ただし、相続欠格に当たる事由はそれほど広範囲ではありませんし、実際のケースも相続全体の比率からすれば稀と言える状況かと思います。
そうとはいえ、もし相続欠格に当たるのであれば、相続人ではなくなるという大きな影響が生じることになります。「こういった事情があるけれども相続欠格に当たるだろうか?」という疑問がございましたら、ぜひ弁護士へ一度ご相談されることをおすすめいたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。