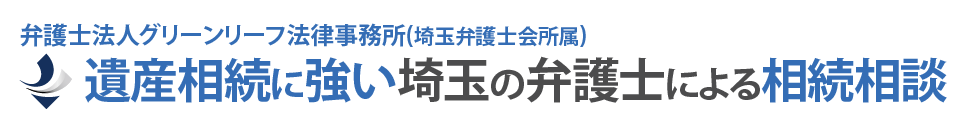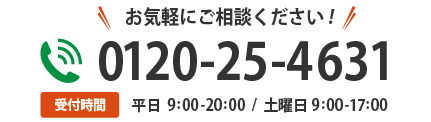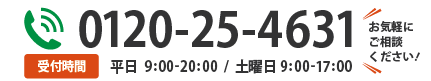法務局の自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言のデメリットを補うことができる公的な制度です。この記事では、弁護士が実際に同制度を利用してみた上で、手続の流れやアドバイス、利用して感じたことなどを紹介します。 2020年から・・・
「弁護士コラム」の記事一覧(8 / 15ページ目)
葬儀費用は誰が払うのか?遺産から支払う方法は?弁護士が解説します!
実は、葬儀費用(葬式代)は遺産から当然に出せる訳ではありません。また、相続人全員で負担する義務があるわけでもありません。この記事では、葬儀費用は法的には誰の負担とされているのか、遺産から支出するためにはどうしたら良いのか・・・
「遺贈」と「相続」って似て非なるもの? 両者の違いを弁護士が解説します
「遺贈」と「相続」は、どちらも人の死亡を原因として財産が移転するものであり、似たような概念と捉えられがちですが、法律上は明確な違いがあります。本稿ではこれらの違いや、遺贈のメリット・デメリットについて、基礎的な事項を弁護・・・
相続争いを防ぐための「終活やることリスト5選」何から始める?タイミングはいつ?を弁護士が解説
「終活」は、自身の残りの人生をより良くするためにも行われますが、相続での争いを未然に防ぐために、被相続人の立場からの配慮としても行われます。終活とは何か、何をやるべきか、いつ始めるべきかなど、弁護士がリストと共に解説して・・・
「民法904条の3」による特別受益・寄与分に関する主張の期間制限について
遺産分割には期間制限がなく、被相続人死亡後、何十年も経ってから遺産分割を行うことも可能です。しかし、令和5年4月1日からは、民法904条の3により、特別受益と寄与分に関する主張について期間制限が設けられたので、注意が必要・・・
数次相続とは? 再転相続や代襲相続との違いやその特徴を解説
相続が複数重なって生じてしまう「数次相続」の場合、当事者関係や権利関係が複雑化し、相続問題の解決が難しくなる傾向があります。この記事では、数次相続とはどのような状況か、その特徴を解説し、数次相続への対応方法について述べて・・・
相続財産管理人と相続財産清算人
以前、「相続人がいない場合にはどうなる?」というコラムを作成しました。 その際取り上げた「相続財産管理人」と「相続財産清算人」について、さいたま市大宮区で35年以上の歴史を持ち、「相続専門チーム」を擁する弁護士法人グリー・・・
空き家の放置はリスクだらけ! 空き家の放置で発生する可能性のある法的責任について
空き家を放置すれば近隣住民に多大な迷惑をかけるだけでなく、空家法上の勧告を受けて税金が最大6倍になったり、管理不全から生じた損害を賠償する必要があったりと、リスクがいっぱいです。それらのリスクと空き家問題を回避する方法に・・・