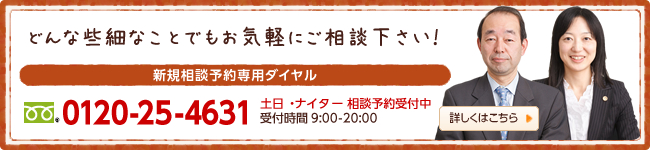この記事では、「公正証書遺言は無効にならない」といったイメージについて、無効になるケースは存在しないのか、なぜそのようなイメージがあるのかについて、公正証書遺言作成の現場を踏まえて解説したします。
公正証書遺言は無効になるのか?

「公正証書遺言は無効にならない」という話を聞いたことはないでしょうか。
この記事では、なぜそのような話が出てくるのか、そもそも遺言が無効になる場合というのはどのような状況なのか解説し、公正証書遺言の無効について考えていきたいと思います。
そもそも公正証書遺言とは?

法律上の効果を持つ「遺言(いごん)」には、下記のような種類があります(普通方式遺言)。
①自筆証書遺言(民法968条)
②公正証書遺言(民法969条)
③秘密証書遺言(民法970条)
上記の中では①自筆証書遺言が一番ポピュラーでしょうか。被相続人が亡くなった後、自宅から遺言書が発見された、という場合には、自筆証書遺言であるパターンが多いと思われます。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆(自分の手で書く)をして作成するものです。
一方で、②公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で伝え、公証人が文章に書き表して作成されます。
したがって、自筆証書遺言と公正証書遺言では、遺言書の文章の(実際の)書き手が異なることになります。
一般に、遺言が無効になる場合とは

上記3つのような方法で遺言書を作成し、「遺言」を遺すということは、法律上の効果をもたらす「法律行為」ということになります。
そして、法律行為には、「無効」となり法律上の効果を生じないとする場面が想定されています。
では、法律上の「遺言」が無効となる場合としては、どのような場面があるでしょうか。
遺言の場合、大きく2つ、無効の場面が想定されます。
1つは「要式性の不備」、もうひとつは「遺言能力の欠如」です。
① 要式性の不備

遺言は、法律(民法)で定められた法律行為です。そのため「このように作成しなければならない」といったルールが定められています。
要式性の不備とは、そういったルールが守られていないということです。
例えば、自筆証書遺言の場合、
●遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自筆しなければならない
●押印が必要
といった基本的なルールが存在します。
このルールに反して、遺言の全文をワープロ打ちしたり、日付を「令和〇年〇月吉日」と曖昧にしたりすると、遺言は無効ということになります。
② 遺言能力の欠如

遺言は法律行為であることから、法律行為をするための意思能力が必要となります。
ざっくりといえば、物事が分からない赤ちゃんには、法律行為である遺言はできないということです(ちなみに民法は、満15歳に達した者に遺言をすることを認めています。民法961条。)
遺言をするために必要な意思能力は、遺言能力と呼ばれています。
遺言をするときには、この遺言能力が必要となります(民法963条)。
では、遺言能力というのは、どのようなものを指すのでしょうか。
これについては、法律上に明確な定め・定義があるわけではありません。法学者の中でも様々な定義が試みられています。
なお、裁判例では「遺言者が遺言事項(遺言の内容)を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力(意思能力)」であるとするものがあります(東京地裁平成16年7月7日判決)。
学者の説や上記裁判例のいう定義をざっくりまとめると、
●これから自分がどういう内容の遺言をしようとしているのか
●その遺言をすると、将来どんな効果がもたらされるのか
といったことが分かる判断能力があるかどうか、ということだと思われます(厳密な考え方ではありませんので、あくまでイメージとして捉えて頂ければと思います。)。
こういった「遺言能力」が、遺言した当時に遺言者に無かった場合には、遺言は無効ということになります。
本題:公正証書遺言は無効にならない?

それでは、本題の「公正証書遺言は無効にならないのか?」について見ていきたいと思います。
要式性の不備は極めて生じにくい
上記でも見てきたように、遺言には「このように作らなくてはならない」といったルールが定められています。
それは公正証書遺言の場合も同様です。
そのため、理屈上は、公正証書遺言としての要式を満たしていなければ、公正証書遺言も無効になります。
しかし、公正証書遺言は、遺言者から遺言内容を公証人が聞き取って、公証人が実際の文章として仕上げます。
公証人は、公正証書遺言を含めた公正証書を作成するプロです。
多くの場合、裁判官・検察官・弁護士・司法書士等の法律関係の仕事を長年行ってきた人が公証人になります。
公証人は法律や公証実務に精通していますので、要式を間違えることはほとんど無いと言えるでしょう。
遺言能力が欠けていれば公正証書遺言も無効になる

前述のとおり、遺言能力が欠けている状態で作成された遺言は、法律的には無効となります。
それは、自筆証書遺言の場合も、公正証書遺言の場合も同様です。
実際にも、遺言能力が十分でなかったということで、公正証書遺言が無効とされたケースは存在します。
例:東京高裁平成25年3月6日判決
昭和55年に妻に全財産を相続させる内容の自筆証書遺言を作成していた遺言者が、平成19年に実妹に全財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成したが、遺言作成時に遺言能力が無かったことを理由に(後の)公正証書遺言が無効とされた。
では、「公正証書遺言は無効にならない」というのは、全く根拠のない、嘘のイメージになるのでしょうか。
これはあくまで私見ですが、公正証書遺言は「無効にならない」というより、「無効になりにくい」というのが、正確なところと思っています。
それは、上記の要式の不備がほとんど生じないという理由だけでなく、遺言能力という側面からも、無効になりにくいと思われるのです。
以下、詳しく見ていきます。
1 公正証書遺言はどのように作成されるのか?

公正証書遺言の作成の流れは、おおざっぱに言えば以下の通りとなります。
① 遺言者などから公証人へ、遺言書作成の依頼・相談
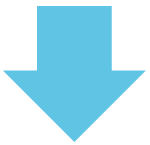
② 遺言者などと公証人の間で、具体的な遺言書案の作成・修正のやりとり
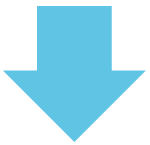
③ 遺言当日(公正証書遺言の作成日)、遺言者から公証人に対し、遺言の内容を口頭で説明(口授)
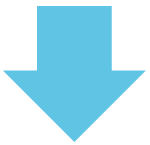
④ 公証人から遺言者に対して、遺言が遺言者の真意であることの確認、および公正証書遺言の読み聞かせ・閲覧による内容の確認
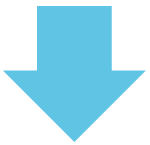
⑤ 遺言者、証人、公証人による署名・押印
この中でも、特徴的かつ公証人が重視しているのが、③の「口授」と呼ばれる手続きです。
参考:日本公証人連合会HP「Q4.公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか?」
2 「口授」って何?

公正証書遺言をする際には、遺言者から公証人に対して、遺言の趣旨(遺言の内容)を「口授」することとされています(民法696条2号。ただし口がきけない人のための代替手段は用意されています。)。
口授というのは、要するに口頭での説明です。
遺言書作成の当日は、遺言者自身が、改めて遺言の内容を説明する必要があります。
これは何も遺言書の文案を暗唱しなくてはならないということではありません。
遺言の内容にもよりますが、「自宅は長男に、預貯金は長女に」のように大体の内容を説明できれば良いということのようです。
遺言者自身に、対面で、遺言の内容を説明させることで、公証人は遺言者が真にその内容の遺言を遺したいのだということを確認しているということです。
3 公正証書遺言作成の一連の流れが、遺言能力をある程度担保している

上記①・②のやりとりについては、遺言者自身が行うこともあれば、弁護士などの士業や銀行等がサポートすることもあるのが実情です。
しかし、③の口授だけは、民法上要求されている要式であり、遺言者は誰の助けも得ずに行わなくてはなりません。
例えば、普段は遺言者のご家族が遺言者の生活をサポートしているといった場合にも、遺言者の口授を助けることはできません。
(証人にならない限り)原則として遺言作成の現場に立ち会うことも許されません。
公証人は、上記の口授、それから遺言作成に付随する様々な手続き(本人確認や読み聞かせ、署名押印)、それらのやりとりを介して、何か不審な点はないか、すなわち遺言能力に問題は無いかを、暗にチェックしているといわれています。
そして、遺言能力に問題があると判断した場合には、公正証書遺言の作成を中止しているとのことです。
もちろん、口授のやり方や当日の遺言者の状況等によっては、本当は遺言能力に問題があるにもかかわらず、公正証書遺言を作成し終えてしまうこともあり得るところです。
そのため、上記の裁判例のように、公正証書遺言であっても最終的に裁判所で無効と判断されるケースは存在します。
しかし、公証人によるある程度のチェック(スクリーニング)があることで、遺言能力に問題がある一定のケースでは、遺言書作成ができないで終わるということもあると思われます。
こういった実際上のスクリーニングがあるために、「公正証書遺言は無効にならない(なりにくい)」というイメージが出来上がったのではないでしょうか。
まとめ:公正証書遺言は無効に「なりにくい」

以上見てきた通り、公正証書遺言は、無効に「ならない」のではなく、無効に「なりにくい」遺言方法です。
したがって、自筆証書遺言に比べれば、のちに争いになりにくい方法だと言え、慎重に遺言を遺したいという場合には特におすすめの方法と言えます。
公正証書遺言を作成する場合には、遺言の内容・文案の作成のほか、公証人との間で作成手続にかかわるやりとりや調整も必要となります。
弊所に公正証書遺言の作成をご依頼される場合には、お客様からご事情やご要望を丁寧にお伺いし、必要書類の収集のサポートや、これらの作業・手続の代行、証人としての公証役場への同行などを行いますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。